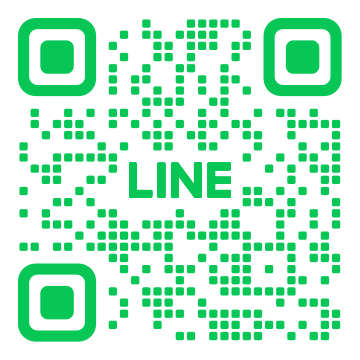令和7年相続税路線価が発表されました。
- niokantei
- 2025年7月3日
国税庁は1日、土地の相続税や贈与税の算定基準となる令和7年分(1月1日時点)の路線価を発表しました。全国の平均変動率は前年比2・7%増と4年連続で上昇し、現在と同じ計算方法で集計している平成22年以降で最大の伸び幅となり、インバウンド(訪日客)需要や駅周辺の開発が後押しした形となりました。ただ、地方の一部では下落傾向が続いている模様です
約31万8千地点の標準宅地を対象に調査。都道府県別では、東京の8・1%増が最も大きく、沖縄6・3%、福岡6・0%と続きました。下落したのは12県。中でも新潟(0・6%)、山梨(0・4%)、奈良(1・0%)などでは下落幅が拡大となった
伸び幅が大きかったのは、別荘地や観光先として訪日客に人気のエリアで、長野県白馬村が32・4%、北海道富良野市30・2%、東京・浅草29%を記録しました。
全国の最高価格は、40年連続で東京都中央区銀座5丁目の文具店「鳩居堂」前にある銀座中央通り。1平方メートル当たり4808万円で、前年に比べて8・7%の上昇となりました。
今回の調査では、昨年発生した能登半島地震の影響を初めて反映。石川県全体は0・7%上昇、被害の大きかった輪島市朝市通りは16・7%のマイナスとなりました。
滋賀県の動向は、二年連続の上昇となり、最も上昇率の大きかったのは草津の6.1%でした。
県内路線価トップは28年連続で草津駅前広場(東口)で35万円(6.1%)でした。他方、今津署管内(高島市)は唯一下落で推移しており、県内路線価の二極化が進んでいるものと思われます、
この結果を踏まえて地価調査の作業に反映します(^^♪
 077-516-8907
077-516-8907